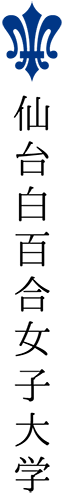本学カトリック研究所 前橋女子高「総合的な探究の時間」で生徒のインタヴュに答える
群馬県立前橋女子高等学校の2名の女子生徒によるインタヴュに、本学カトリック研究所が応じました。
前橋女子高等学校は、群馬県の中でトップクラスの公立女子高校。6月中旬に同校3年生のYさんから次のような丁寧な文面で研究所に問い合わせがありました。
| 「前橋女子高校では、SSH(スーパーサイエンスハイスクール)の授業「総合的な探究の時間」の一環として、グループでテーマを設定して研究活動に取り組んでいます。私たちは、キリスト教の、特にカトリックの死生観や現代の尊厳死、安楽死法との関係について調査をしております。 この調査を行う中で、仙台白百合女子大学カトリック研究所様にインタビューのご協力をいただけないかと考え、メールいたしました。」 |
宮崎正美所長が対応し6月24日(月)のオンライン・インタヴュの実施となりました。
──カトリック教会の、人間のいのちに関わる生命倫理の諸問題に対する考え方の根底には、人間の意志だけでいのちを支配することがあってはならない、いのちとはその本人の所有物ではなく、神からの賜物として神秘の側面を有するとの前提がある。したがって医の現場では、患者本人だけでなく、医療従事者、患者の家族など人間関係のなかで最善が求められねばならない。他方カトリック教会は、時代状況に対応して医学の進歩に鑑みつつ、現実に即して一人ひとりがその人らしく生きられるにはどうしたらいいかを考え続けている。──このように前置きしてインタヴュが始まりました。
「1983年の新しい教会法では、自殺者の埋葬に関する規定が変わったそうですが?」
大学生でもなかなか気づかない重要な点に注目しつつ、高校生たちは予めいくつかの質問項目を考えていました。
教会法は、たしかにカトリック教会の具体的な対応の方向性を示す、大切な道しるべの一つですが、それに先立って世界中の現代カトリック教会の変革の源泉となった、第二ヴァティカン公会議(1962-65)の実りとして、新しい教会法典が公布されたのです。さらにその根底には、死から復活へといたる人間のいのちの神秘に、人間に対する神の愛をみる方向性の考えがあります。
「カトリックの影響が大きい国での安楽死の合法化の背景には無神論者の増加があるのではないか」
西欧の無神論者の増加は事実ですが、中南米のカトリック教会の影響が大きい国でも安楽死の合法化の例があります。国ごとの合法化には、さまざまな考えを認め合うべきだ、という多様性の考えが背景に多くみられるようです。国家として法的に統一して社会秩序を維持する一方で個々人の意志を制限することに問題の一つがあります。個々人が自由な意志をもって一つの人格としてその人らしく生きることに、本来の人間の在り方の方向性をみていますので、必然的に個々人の人格の違いに由来する多様性を認め合う社会は、現代カトリック教会の教えに反しません。しかしそれは、神の賜物としての人間のいのちを大切にする考えだからこそ、本人であれ他の者であれ限られた能力しか持ち合わせていない人間の判断によって、人間のいのちを奪う行為はあってはならないとしています。
インタヴュは予定時間を超えて90分に及びました。 綿密に下調べして臨んだ高校生たちの考察に、少しでも役に立ったならば幸いに思います。